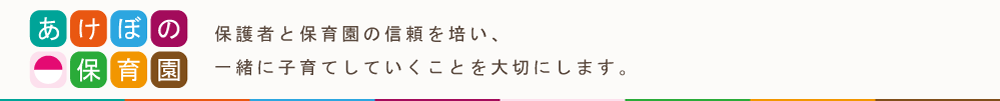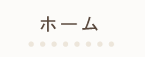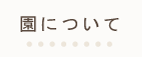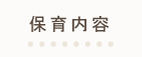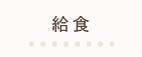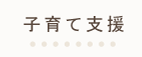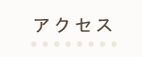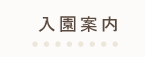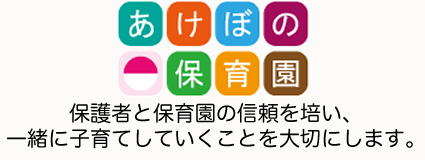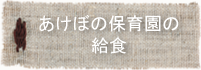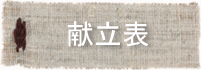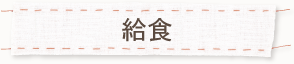
あけぼの保育園の給食
低農薬・無農薬有機野菜を中心とした野菜の利用、抗生物質を使用せず
飼料の安全性にもこだわった肉、その他国産品を中心とした添加物などを使用していない
自然で安全でおいしい食材を使うことをこころがけています。
これらの理由から園の食材はほとんどのものを生協からとっています。
手作り

昼食、おやつ、延長保育の補食・夕食、離乳食、アレルギー食すべて園内の調理室で手作りしています。
献立のなかで大切にしたいこと
日本の風土に合った、日本人の体にあった、昔からの味「和食」をこどもたちに伝えたいと考えています。
旬の新鮮な味を楽しむこと
日本には春夏秋冬があり、四季折々にいろいろな食材を楽しめます。
最近はいつでもいろいろな食材が店頭に並んでいるのが普通になっていますが、旬の食材はうまい!安い!栄養価が高い!とうたわれ、その季節に自然からとれた作物の味は格別です。
根菜類をできるだけ多く摂ること

大根、人参をはじめとする根っこの部分を食べる野菜は繊維質を多く含み、熱に強いビタミンを多く含みます。あけぼの保育園ではいろいろな調理方法で給食に根菜類が登場します。
ビタミン類は体の調子を整える大切な栄養素です。ヒトの体のなかでは作り出すことができませんので、食べ物から摂る必要があります。
海藻・小魚の多い給食
海藻・小魚には歯や骨を丈夫にするカルシウムをはじめとした多くのミネラルが含まれています。
ミネラルは体を作る主成分や体の作用の補助をする大切な成分です。
また、海藻や小魚は適度な歯ごたえがあるので、顎をきたえて脳の活性化につながります。
主菜は魚を中心とした献立

魚に含まれる油には体に良質な成分が多く含まれています。
そのほか、毎日食事の前に散歩に行きみんなで向かい合ってわきあいあいと給食を囲み、食事を楽しむことを大切に考えています。
食べる意欲やおいしいという味覚を育てる意味でも、食事に向かう姿勢や環境を大切に考えています。
離乳食

スプーンひとさじからの離乳食準備期から初期、中期、後期、完了期と時期だけではなくその子の発達にあわせた形態で、食べ具合を見ながら作っていきます。
アレルギー食
医師からの指示書のもとに、食べられる食材を利用して除去食・代替食を作ります。
食事の際は、調理室と担任で毎食確認し合ったり、食器やトレーを変えることで安全に提供できるようにしています。
行事食
ただいま、準備中です。
食器
重さやぬくもりが手になじみ、家庭的な雰囲気を出せるよう陶器の食器を利用してます。
給食室より
2025年度1月
和食を知ろう~おせち料理~
日本各地で「文化」として色濃く残っているおせち料理。地域ごとに様々な特徴がありますが、新年におせち料理を食べることで健康長寿を願う点は共通しています。
重箱に彩りよく詰められた料理には、
黒豆 豆に過ごせますように
かずのこ 子孫繁栄
昆布巻き 喜ぶ
きんとん 金運 など
一つひとつに様々な意味があり、願いがあります。こどもと一緒に食べながら、伝えていきたいですね。
あけぼのクッキング ~松風焼き~
【材料】
鶏ひき肉 150g
豚ひき肉 90g
・玉ねぎ 小1/2個 ・サラダ油 少々
木綿豆腐 1丁の1/5 ・パン粉 1/2カップ
しょうが汁 少々 ・酒 小さじ1
砂糖 小さじ2/3 ・しょうゆ 小さじ1/2
みそ 小さじ1と1/2 ・白ごま 大さじ1
【作り方】
- 木綿豆腐は、ザルに入れ水分を切ってからつぶす。
- 玉ねぎは、皮をむいてみじん切りにして、サラダ油をひいたフライパンで炒める。(冷ましておく。)
- 白ごま以外のすべてをボールに入れ、よく練り合わせる。
- 天板にクッキングシートを敷いて3を平らにのばし、白ごまを振り、200度のオーブンで約20分 竹串で刺して透明な汁が出るまで焼く。
- 食べやすい大きさに切り分けて皿に盛る。
2025年度12月
こどもと「共食」をするメリット!
みんなで一緒にご飯を食べる「共食」には数えきれないほどのメリットがあります。
- バランスの良い食事をとりやすい
→色々な食べ物がテーブルに並びます。大人もこどもも栄養バランスの取れた食事がしやすくなります。 - 苦手なものにも挑戦
→目の前で親が食べる姿を見ると、苦手なものも「食べてみようかな~」と挑戦する思いもわいてきます。こどもの苦手意識は薄れていくことでしょう。 - コミュニケーションの時間になる
→みんなで食卓を囲み、一緒に食事をすれば普段の会話はもちろん、食べ物の会話も弾みます。食事に関心を持てる機会になるということ、それはもう立派な食育です。
このほかにも親が食べる姿を見てテーブルマナーを学べ、作る人はお料理も片付けも効率よくできます。
家族そろって食事をすることは現代人にとって意識していかなければならないものになってしまいましたね。
誰かと「共」に「食」事をする「共食」はこどもの成長にとってとても重要です。
酸味が意外と人気~白菜のコールスローサラダ
大人2人・子ども2人分
白菜…150g
きゅうり…3分の1本
人参…3分の1本
コーン缶…小さじ山盛り1杯(約18g)
ドレッシング
酢…小さじ1(5g)
サラダ油…小さじ1と2分の1(4g)
食塩…一つまみ(1.2g)
砂糖…二つまみ(1.8g)
<作り方>
- 白菜・きゅうり・人参を千切りにします
- コーンと①を軽く湯通しします
- 水気をよく絞りボウルに移し、調味料を合わせたドレッシングで和えたら完成
2025年度11月
一気に秋も深まってきましたね。
みなさん、普段の食事を良く噛んで食べていますか?
食べ物を良く噛むことはいいことがたくさんあります。
普段の食事の中で「良く嚙む」を意識して取り入れてみて下さい。
良く噛んで食べよう!
食べものを良く噛むと
- 食べすぎを防ぐ
- 消化吸収を良くする
- あごの筋肉を動かすことで、 脳の血流が増え、脳を活性化する
- 噛むことにより出る、唾液の働きで虫歯を予防する
良く噛むことを意識して食べましょう!
あけぼのクッキング ~れんこんの金平~
【大人2人・こども2人】
材料 ・れんこん 約1個 ・人参 約1/3本
・サラダ油 大さじ1/2 ・砂糖 小さじ2 ・醤油 小さじ1
・本みりん 小さじ1 ・だし汁 適量
<作り方>
- れんこん・人参は皮を剥いて0.5mm幅に いちょう切り又は半月切りにする。
- 鍋に油をひいて①を炒める。
- 油がなじんだら、調味料を入れる。
- だし汁、なければ水を浸るくらい入れ、煮つめる。
- 水気がとび、野菜に火が通ったら完成。
最後にごま油をひとまわししてもおいしいです!
過去の給食室よりはこちらからご覧になれます。
献立表
幼児
バックナンバー
・2026年1月・2025年12月・2025年11月・2025年10月・2025年09月・2025年08月・2025年07月・2025年06月・2025年05月・2025年04月
乳児
バックナンバー
・2025年12月・2025年11月・2025年10月・2025年09月・2025年07月・2025年06月・2025年05月・2025年04月